2025年3月22日、日本のラジオ放送は100年の節目を迎える。前編では、その歩みを振り返り、ラジオが社会にもたらした価値と影響について探った。本稿では、ラジオ放送波の強みと課題を掘り下げ、次の100年に向けたラジオ技術の可能性を考察する。ラジオは、ただ音を届けるだけの存在ではない。広域伝搬、輻輳しない安定した情報伝達、災害時の強みなど、他のメディアにはない特性を持つ。その価値をさらに高めるため、当研究室では、受信感度向上技術や無給電ラジオ、ユニバーサルデザインを取り入れた次世代ラジオの開発に取り組んでいる。本稿では、「誰もが、どこでも、確実に情報を受け取れる未来のラジオ」を実現するための技術的展望を示すとともに、ラジオというメディアを通じて、日本発の新たな科学技術の革新へとつなげていく可能性について述べる。
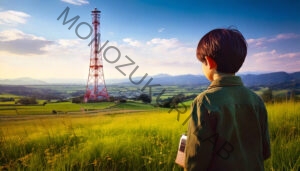
1. リスナーへの「一対多」情報伝達の強み
輻輳(ふくそう)しない安定した情報伝達
インターネット通信は、多くの人が同時にアクセスすると回線が混雑し、情報が遅延したり、接続できなくなるといった問題が発生する。特に災害時には、通信インフラが一時的に麻痺し、情報が得られなくなることもこれまで度々起こったのは事実であり教訓でもある。しかし、ラジオはどれだけ多くの人が同時に聴いても輻輳や遅延が発生しない。送信側が情報を発信すれば、それをすべての受信者が一斉に、同時に受け取ることができる。この「輻輳しない情報伝達」こそが、ラジオの最大の強みである。
AMラジオはより広範囲に情報伝達可能
ラジオ放送は、電波の到達範囲が広いという特性を持っている。特にAM放送は、長距離伝搬が可能であり、都市部から離れた山間部・離島・海上でも安定して受信できるメリットがある。例えば、FMラジオ局の電波が受信出来ない地点でも、AMラジオ局の電波は地表波や電離層反射波による伝搬、さらに海上伝搬により、数百キロ先まで届くため、都市部に限らず、通信インフラが整っていない地域にも情報を届けることができる。近年、大きな災害が起こるとNHKは全国放送で災害情報を伝えてくれるので、どこかのNHKのAMラジオ局が受信できれば災害情報を受信できる状況がある。
電波が届けば、確実に情報を取得できる
インターネットは、スマートフォンやパソコンといった端末が必要であり、通信契約やWi-Fi環境がなければ利用できない。しかし、ラジオは受信機があれば無料で情報を取得できる。特に、災害時にスマートフォンや端末の電池が切れてしまった場合でも、ラジオは乾電池式や手回し充電式、さらに無給電ラジオなら電源不要で使用できるため、確実に情報を得られるという強みがある。
2. 災害時に役立つラジオの進化
南海トラフ地震などの大規模災害が発生した場合、通信インフラの寸断、停電、津波による被害が予想されるため、確実な情報取得手段としてラジオが重要である。停電時にはテレビは使え無いし、自宅や職場、外出先のネットワークやルーターが使える保証がない。普段、ラジオは使わない人でも、災害時のラジオの価値は大きい。テレビ、スマホが使え無い状況で、命を守る最後の情報取得手段になる可能性が高いことは、過去の災害時での事実を思い出してほしい。このラジオの強みをさらに進化させる研究を探究しているので紹介する。
緊急時の情報伝達と自動切り替え機能
研究室では、通常放送中でも、地震速報や津波警報が発せられた瞬間に自動で切り替わるラジオを探究している。こうしたラジオは現在、一部に既に存在はしているが普及しているとは言えない。緊急地震速報のリアルタイム放送、津波警報や避難指示の即時伝達、避難所の情報やライフライン復旧状況の提供など、リスナーが確実に重要な情報を受け取れるようにする必要があるのでその方策も含めて探究している。
無給電ラジオの開発
研究室では、電源がなくても動作する無給電ラジオの研究を進めている。電界強度が比較的強い地域ではラジオ放送波のエネルギーを使って、電池や外部電源なしでラジオ放送を受信できる。スマホと連携できるので、スマホを使って地上放送波を直接受信することもできる。
3. 受信感度向上技術の開発
例えば、日本の人口の1/3が居住する関東平野ではラジオ受信には何の問題がなくても、地方や山岳部では問題になる。当研究室では、より良い受信環境をスマートに改善する技術を開発し探究している。これらの技術により、都市部での一次非難所、都市部や山間部、離島、半島で快適に聴取できる環境を構築できると考えている。サービスエリアが増えれば、放送事業者にとっては中継局を作るコストを削減できる可能性がある。
無給電ラジオと電波発電技術
電波発電(エネルギーハーベスティング)とは、周囲の電波や環境から微弱な電力を回収し、電子機器を動作させる技術である。これを放送波に応用し、電源が不要な「無給電ラジオ」や「電波発電技術」の開発を進めている。電波発電効率を高めることはアンテナ技術を高感度化することの探究なので、培ったアンテナ技術を活用することで、ラジオ難聴地域の受信性改善のためのアンテナ技術として役立てられる。
高感度簡易アンテナでリスナー側の受信環境を改善
ラジオの受信品質は、放送局からの電波の強さだけでなく、リスナー側の受信環境によっても大きく影響する。建材の種類にもよるが、室内では電波が弱くなりやすく、また電気製品から発生しているノイズの影響を受ける場合がある。これはAMラジオだけでなくFMラジオでも起こる。AMラジオは木造の建物内では受信性は良いが、鉄が関わる部材を使った建物内では受信感度が弱まる電波の性質がある。また、FMラジオは電界強度が強い地域では雑音が少なく音質は良いが、電界強度が弱い地点では耳障りなノイズが増える。AMラジオやFMラジオにはそれぞれの弱点があるが、それぞれには必ず解決手段がある。研究室では、受信環境をスマートに向上できるAM/FMラジオ向けの生活空間を考慮した「スマートアンテナ」を探究している。山間部や電波の届きにくい地域でも、災害時にはラジオから情報を聴取できる環境を構築できると考えている。
4. ユニバーサルデザインなスマートラジオ開発
ユニバーサルデザインとは、「年齢や障がいの有無にかかわらず、すべての人が快適に利用できる設計」のことを指す。ラジオは、多くの人に情報を届ける重要なメディアであるが、現在の市販ラジオの多くは、高齢者や障がいのある方にとって使いづらい仕様になっていることが課題である。研究室では、「誰もが簡単に、安全に、確実に情報を受け取れるラジオ」を探求している。高齢者向けの簡単操作、視覚障がい者向け機能、聴覚障がい者向け機能などを持っている。
ハイブリッドラジオの研究
通常時はインターネットを利用して放送を受信し、災害時には自動的にラジオ放送波(AM/FM)に切り替える技術である。現在、スマートフォンやインターネットを使って音楽やニュース、ポッドキャストなどを聴くスタイルが増えている。しかし、災害時には通信回線が混雑し、輻輳により繋がらない、ネット接続が途絶えてしまうなど、使える保証が無い。平常時はインターネットラジオなどを利用して、多様なコンテンツを楽しめ、災害時やネットが使えなくなると、自動的に地上波ラジオに切り替わり、確実に情報を「受信」できる。ネットに障がいがあっても確実に災害情報を取得できるラジオが実現できる。
健康促進メディアとしてのラジオ
ラジオは情報伝達だけでなく、健康維持やメンタルヘルスの向上にも貢献している。ラジオ体操は長年愛されている健康プログラムとして、全国民の健康維持に貢献している。高齢者でも無理なくできる軽い運動として、多くの地域で活用されている。例えば、ラジオ体操を習慣化することで、生活リズムの安定や認知症予防にも役立てられる可能性がある。全国には、難聴地域でラジオ放送波が届かない、CDなどでラジオ体操を行わざる終えない地域がある。受信性の改善により、ラジオがあれば手軽にラジオ体操が楽しめるようになる地域を増やせる。
5. AMラジオの価値について
AMラジオ放送からFMラジオ放送への移行の問題
AMラジオ放送が始まって100年経った今、AMラジオ放送局が減退しようとしている。放送事業者の送信インフラの維持コストの課題から、FMラジオ放送に移行しようとしている。放送のコンテンツだけを考えるなら、AMラジオ放送がFMラジオ放送に移行しても大きな問題は無い。しかし、ここにほとんど話題にされない問題がある。それは、AMラジオとFMラジオの電波伝搬性に大きな違いである。
AMラジオをより正確に表現すれば、「中波帯を使ったAM変調によるラジオ放送(中波放送)」、また、FMラジオとは、「超短波帯を使ったFM変調によるラジオ放送(超短波放送)」である。中波放送と超短波放送の顕著な違いは、電波伝搬性にある。中波放送波は、送信周波数が低く、波長が長く(詳細略)、地表波や電離層反射波などの伝搬、さらに、海上伝搬により電波が広範囲に伝搬する。見通し範囲を超えて、地平線の向こう側まで伝搬する。国内では電波法により500kWもの送信出力が認可されている。一方、超短波放送波は、送信周波数が高く波長が短く(詳細略)、直接波による性質で伝搬し、見通しの範囲内で電波が直線的に伝搬する性質がある。つまり、AMラジオ放送がFMラジオ放送に移行することで、電波の到達範囲が格段に減少してしまう。リスナー側にとって問題になる。この問題は、例えば、東京スカイツリーや東京タワーからのFMラジオ放送の電波を利用する関東平野や電界強度の強い都市部での人々には、AMラジオ放送がFMラジオ放送に移行しても大きな問題は起こらない。AMラジオ放送の電界強度も強い。問題は、地方や半島、離島などで、これまでAMラジオ放送が(なんとか)聴けていたリスナーや、普段からFM放送自体が聴けていなかったリスナーにとって、AMラジオ放送がFMラジオ放送に移行することは、AMラジオ放送の受信が困難になることから、ラジオ難聴地域が増加するので情報弱者が増えてしまう。これまでFMラジオが受信できるが、AMラジオ放送があまり受信できない地域では、AMラジオ放送がFMラジオ放送に移行しても問題は起こらない。
AMラジオでしか成し得ない理由
AMラジオ放送(中波放送)の最大の特徴は、「地上放送波の広域伝搬性」にある。すなわち、AMラジオ放送は、送信所からの「直接波」、地表を伝わる「地表波」、大気中で反射される「電離層反射波」などの電波伝搬により受信できる。夜間には電離層での反射が強くなり、数百キロ~数千キロ先まで放送波が届くこともあるのが特長である。一方、FMラジオ放送(超短波放送)は、AMラジオ放送よりも音質が良く、ノイズの影響を受けにくいといわれるが、ノイズを受ける状況もある。FM変調の原理上、電界強度の弱い状況ではノイズが増えるので放送が聴きづらくなる問題もある。FMラジオ放送波は直進性が高いため、送信アンテナから見通し範囲を越えた地点や山間部、ビルの陰などでは受信しにくくなるという性質がある。
自然災害の多い日本では、災害時に信頼のある放送局からの正確な情報を確実に得られるかどうかは命に関わる問題である。その教訓は関東大震災にあったことを忘れない。過去の大災害時から言えることは、停電を併発するケースが多い。災害時の「停電」は想定の範囲と考え、テレビ、スマホが使え無くなった場合のためにラジオを持っておくべきである。ただ、ラジオがあっても、放送波自体がそこに到達していなければ、ラジオの受信感度をいくら上げてもラジオは受信できない。NHKの経営に関する情報には、「NHKは公共メディアとして、“いつでも、どこでも、誰にでも、確かな情報や豊かな文化をあまねく伝える”ことを役割として担っています」とある。「いつでも」、「どこでも」、「確かな情報」、「あまねく伝える」を実現するメディアは何か。「いつでも」:停電によらない、「どこでも」:電波の広域伝搬性、「確かな情報」:ねつ造されない放送波の強み、「あまねく伝える」:電波の広域伝搬性、であることを考えたら、テレビでもスマホでもない、FMラジオでもない、AMラジオでしか成し得ないことになる。
6. ラジオを通して科学技術の発展に繋ぐ
AMラジオ放送のデジタル化
地上放送波のワイヤレス性には、有線ケーブルのケーブルテレビや光ケーブルなどの情報断絶の問題が起こらない強みがある。耳で音声を聴く従来の放送から、デジタル技術と組み合わせたワイヤレスなデジタル放送によるAMラジオ放送が電波法の整備などから認可されれば、音や光、文字情報と連動させたラジオ受信機がすぐに実現できる。スマホでは出来ない、成し得ない機能が簡単に実現する。世代や障がいを越えて、ラジオの普及にも貢献する。情報量を上げるために、高い周波数を利用したデジタル技術が最先端技術として進化すればするほど、中波帯のような低い周波数を利用したラジオの重要性はより一層高まることになる。高い周波数では実現できない広域電波伝搬性は、低い周波数の電波にはあるからであり、より快適な通信インフラの発展には共存が必要になるからである。
新たな科学技術の礎を築く契機へ
総務省のページには、「電波は目にみえませんが、石油や石炭などと同様、自然界に存在する天然資源です」とあるが、その通りだと思う。それぞれの周波数帯ごとに、電波の性質は異なり、それぞれの周波数帯の電波伝搬の性質は自然法則に沿い、変えられない。科学技術において、使っている周波数帯が低い/高いと、ローテク/ハイテクとは関係が無いはずである。しかし、競争的研究費の獲得競争において、まるで低い周波数帯を使う技術はローテクな枯れた技術と誤認され、例えばより高い周波数を用いたテラヘルツ技術などが最先端だとされる認識される状況がある。低い周波数帯を使う技術には、実は、枯れた技術ではなく、未解決なまま「見過ごされた」技術があり、何が本質かを見極めた技術の探究にこそ大きな価値があるはずである。AMラジオとFMラジオに関する研究では、それぞれの電波の周波数帯の特徴があらわれる。常識とされる知見では、実験結果を説明できない現象に多々遭遇する。電波工学の教科書にも無い、通説でも説明できない見過ごされた現象に遭遇する。ラジオ放送100周年とは、「中波帯のAM変調によるラジオ放送が始まって100周年」の意味である。波長の長い中波帯の電波を活用したAMラジオ受信機が、放送局から電波を受信する原理の本質はマイケル・ファラデーが発見した電磁誘導の法則である。一方、FMラジオには別の原理を使って電波を受信している。日本のラジオ放送100周年の今、これまでのラジオ技術から人類の様々な科学の発見と発明の一端を振り返ることができる。歴史を紐解くことで、未解明の現象に光を当て、新たな科学技術の礎を築く契機としたい。
(初稿 2025.3.21)
CANONICAL:
https://monozukuri.his.u-fukui.ac.jp/monozukurilab/2025/03/21/post-8665/
参考(ラジオ放送波に研究に関連する論文など)
各文献のPDFはダウンロード可能です
https://monozukuri.his.u-fukui.ac.jp/monozukurilab/2024/01/24/post-8344/
https://monozukuri.his.u-fukui.ac.jp/monozukurilab/2023/10/14/post-8142/
https://monozukuri.his.u-fukui.ac.jp/monozukurilab/2023/10/23/post-8192/
https://monozukuri.his.u-fukui.ac.jp/monozukurilab/2023/09/11/post-8069/
https://monozukuri.his.u-fukui.ac.jp/monozukurilab/2022/08/30/post-7191/
https://monozukuri.his.u-fukui.ac.jp/monozukurilab/2023/10/03/post-8127/